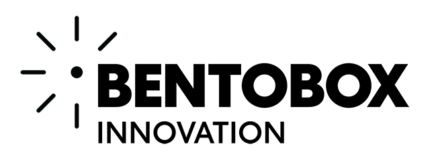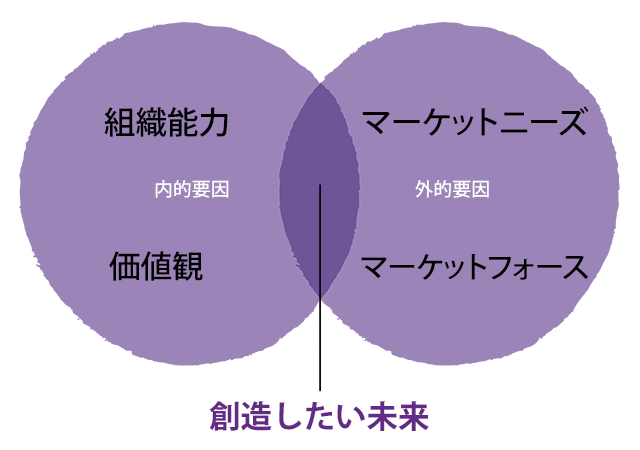4月。新しい期が始まり、チームが変わり、プロジェクトが動き出す。
そんな季節が、またやってきました。
人事異動、新しい顔ぶれ、新しい目標。
でも…チームの“中身”までは変えられているでしょうか?
まだ、“ちゃんと話せていない”
先日、大手総合広告会社のとある事業チームから、
こんなご相談をいただきました。
「新規事業の立ち上げメンバーが集まりました。
でも、まだ面と向かって、ちゃんと話せていないんです」
このチームは、異なるカルチャーや価値観を持ったメンバーが集まり、
新しい組織を生み出すフェーズにいました。
・組織の未来像を、メンバー全員で言葉にしたい
・ただし、自分たちがリードすると話が偏ってしまう
・だからこそ、“対話を支えるツール”が必要だった
そんな背景から、私たちはBentoBoxのIBNF(Imagine Bold New Futures)モジュールを使い、
1日のセッションを設計しました。

「問い」に向き合うことで、見えてきたもの
セッションはファシリテーターなし。
セルフナビゲーションで、メンバー自身が進行していきます。
最初に取り組んだのは、“組織能力”を4つの視点から見つめる問い。
ここで、それぞれが何を見て、どう感じているのかが共有され、空気が変わりました。
参加者からはこんな声がありました:
「最初の問いでチームが見ている景色を可視化できたのが、すごく大きかった」
「企業の価値観と、そこにいる自分の価値観を統合するような構成がよかった」
「得意先のチームビルディングには時間をかけているのに、自分たちのチームづくりは後回しにしていたことに気づいた」
“強み”を言語化した瞬間、方向性が見えた
セッションの終盤では、これからの事業や組織のありたい姿を
「未来ビジョン」として描き出しました。
「自分たちの強みの源泉を深いレベルで言語化できた。
それをどう守っていくか、という“信念”も生まれた」
BentoBoxの設計思想は、「誰かが場を引っ張らなくても、
チーム自身が深い話にたどり着ける」ことにあります。
そこに参加者が実感を持ったことが、何よりうれしいことでした。
今、チームの“立ち上げ”に必要なこと
年度初めのこの時期は、「やるべきこと」が山積みです。でも、
「どう在りたいか」を言葉にしないまま始まるプロジェクトほど、途中で迷走します。
対話の場を、先に作っておくこと。
そして、問いを囲む時間を、丁寧に持つこと。
それだけで、チームは大きく変わります。
BentoBox IBNF モジュールとは?
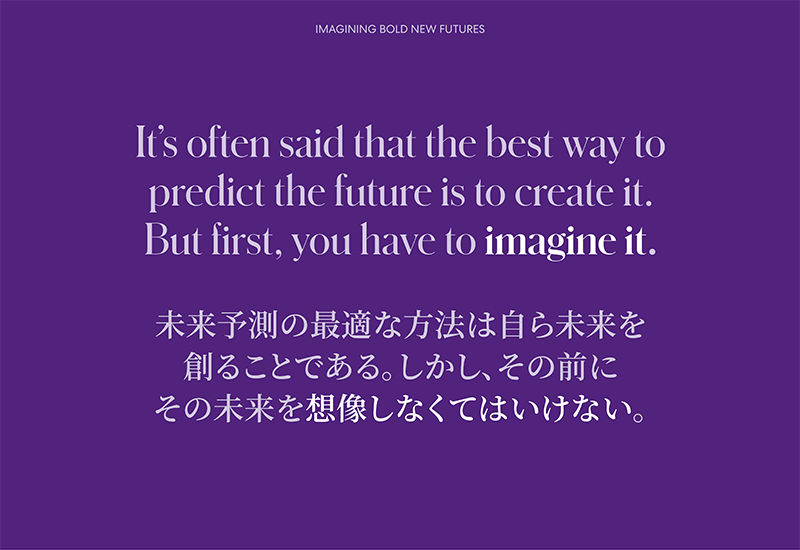
**IBNF(Imagine Bold New Futures)**は、
“実現したい未来”を具体的に描くことで、メンバー間に共通のビジョンと関係性を築いていくセッションモジュールです。
- 異なるバックグラウンドを持つチームで
- 新規事業のビジョンを描きたいとき
- 組織の文化や方向性を共有したいときに
多くの企業にご活用いただいています。
🟡まずは体験してみませんか?
私たちBENTOBOX INNOVATIONのチームは、
「問いから始まる変革」に30年以上取り組んできました。
BentoBoxは、誰もが“使える”ようにデザインされたセルフナビゲーション型の対話ツールです。
📩 お問い合わせはこちら